今年度初めての素話です。
毎年、はじめは何にしようかな?と思いながらお話を選んでいるのですが、今日はたまたま朝の保育室で耳なし芳一のお話で盛り上がっていたということを聞きました。「今度絵本を探してくるね」と言ってくれていた保育士さんには申し訳ないのですが、横取りさせてもらいました。(Mさんごめんなさい)
たんぽぽグループとなった子どもたちは、今年の2月頃に何度かお話を聞くぐらいしか経験がないので、短めのお話を選んでみました。
こがねの斧(たんぽぽグループ)

正直者の木こりはこがねの斧を神様からもらうことができるけど、ズルをする木こりはこがねの斧がもらえないだけでなく、普通の斧もなくしてしまうというストーリーです。
「トンツクトン、トンツクトン、これを切ったら昼飯だ」は勝手に決めたフレーズですが、同じフレーズの繰り返しやリズムに乗ったフレーズは視覚情報の極端に少ない素話では大切なコンテンツです。
子どもたちがフレーズで記憶できるようにしてあげると、繰り返しの面白さや話の見通しを持つことなどもできるようになります。
耳なし芳一

琵琶法師の芳一が平家一族の幽霊たちに平家物語を語るストーリーはどこかで一度は耳にしたことがあると思います。
琵琶法師をイメージさせるよりも、芳一の語りを聞きに来た幽霊が、「芳一はどこじゃ、芳一はおらんが耳があるから、耳だけでも・・・」というシーンの恐ろしさに、子どもたちも思わず耳をふさいでしまいました。それでも耳をふさいだ半分ぐらいは目がキラキラして楽しんでいるので、とても可愛らしいものです。
素話と絵本の関係
保育士を目指す学生から「素話をするときにどんなテーマのお話を選んでいるのですか?」「台本とかはあるのですか?」と聞かれることがあります。そんなときには「もしかするとあなたの聞きたいことと違うかもしれないけど、私の考えを話すね」と前置きして、次のような回答をしています。
素話の「テーマ」を選ぶときは半分以下だと思います。素話を聞く子どもたちの様子やそれまでの保育の流れに沿った内容を選ぶことのほうが多いと思います。とにかく、素話の時間が「楽しい時間」と感じられるかどうかが大切だと思っています。
知っているお話だから楽しくないということもなく、知らない話だから楽しいということもありません。だから、同じ話を何度しても良いし、絵本で読んだことがある内容でも良いと思っています。それ以上に、子どもたちの興味関心や成長にフィットしているか?が一番大切だと思っています。
「この年齢の子どもたちにはこのテーマが正解」というものがないため、学生としては「自分がするときにどうすればよいか?」と悩むのだと思います。そんな意図を感じたときには、「自分が一緒に楽しめるかどうか?」で選んだらいいんじゃない?と答えています。
楽しいお話をするときには楽しくなるし、怖いお話をするときには怖がらせたくなります。そんな私の姿を「素話」として子どもたちが楽しんでくれているのだと思っています。
「台本はあるのか?」についても、基本的なストーリーは台本を作りますが、実際に話しているときにはその流れから外れることや、追加することなどいろいろ工夫しています。全て、眼の前の子どもたちの様子に合わせて臨機応変に作り変えています。
こういう話をすると、「そんな事、私には無理・・・」という表情で返事をしてくれる事が多いので、こういう話もするようにしています。
「大人の側が不安になったり、うまくいかなかったと落ち込んでいたら、子どもたちにもそれが伝わるから、大人が「出来た!」と自信を持っているように見せるといいと思います」
本当は失敗している事に気づいていても、それが子どもたちに伝わらなければ、子どもは「そういうものか」と思うでしょう。
子どもたちは○×をつけるために素話を聞いているわけではありません。大人は何かというと「これが正しい」「こうなったら困る」のように見えない正解を求め続けるのですが、もっと今を最もよく生きるようにしたら良いのにと思います。


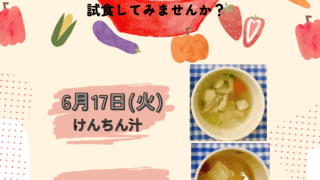








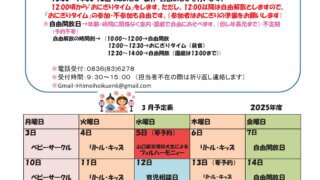

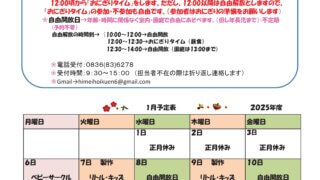


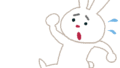
コメント
[…] 今年度初めての素話です。 毎年、はじめは何にしようかな?と思いながらお話を選んでいるのですが、今日はたまたま朝の保育室で耳なし芳一のお話で盛り上がっていたということを聞きました。「今度絵本を探してくるね」と言ってくれてい […] Read More […]